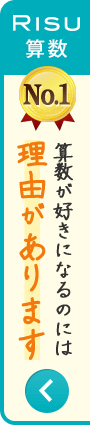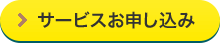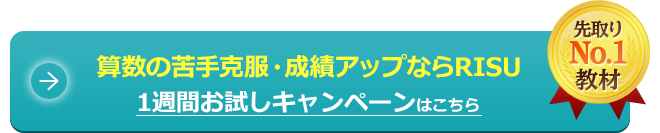子供の叱り方や、叱らずに済む方法があれば教えてください。

道路に飛び出しそうになったり、ボロボロとこぼしているのにお構いなしで食べ散らかしたり、子どもは日々予測不能な動きをするものです。
身の危険につながるような行動について、口うるさくなってしまうのは仕方がないかなと思いつつ、ちょっとした行動についてもついつい感情的に怒ってしまい、反省する日々を過ごしている親御さんも多いのではないでしょうか。
怒るのではなくて上手に叱りたい できれば叱らなくても済むような日々を過ごしたい
この記事では、子どもを指導している塾で日々実践している、叱り方に関して注意すること3つと、なるべく叱らないで済むような方法を5つのステップでお伝えします。
プロの技をぜひ参考にしてみてください。
◆3つの叱り方の注意点
◎叱り方の注意点①感情的にならずに子どもときちんと向き合う
感情的になってしまうと、いつの間にか「叱る」から「怒る」に変わってしまいます。
怒りに変わってしまうとお子さんに威圧感を与え、不安な気持ちにさせてしまいます。
これでは、お子さんは何がいけなかったのか、どうすればいいのか、を理解できなくなってしまいます。むしろ「一刻も早くこの話が終わってほしい」、「この場から離れたい」という気持ちになり、話をきちんと聞いてくれなくなってしまいますので、どれだけ叱ったとしても、その効果は期待できません。
安心感や信頼感は子どもとのコミュニケーションには絶対に必要な要素です。
立ったままなど上から見下ろすのではなく、お子さんに目線の高さを合わせて、目をしっかりと見て、何が悪いのか、やってはいけないことは何なのか理由を説明しながら冷静に諭すように話をすることを心がけてください。
A君を叩いてしまった時に「叩いたりしちゃダメでしょ!」とだけしか言わなかったとしたら、子どもは「A君を叩いちゃダメなんだ」と理解します。これでは、他の子どもを叩いてしまいます。誤った叱り方では、子どもは叩くのをやめません。
何度も何度も根気よく、繰り返し理由を説明することは親にとっても大変な労力がかかりますが、叱った意味があるよう、しっかりと対応していただきたいところです。
◎叱り方の注意点②その場で今起きたことだけを叱る
叱るときに一番気を付けなければならないのは「今行ったこと」に対してに限定し、決して「過去に行ったこと」には触れないということです。
保護者の皆さんはつい「昨日も同じことを注意したよね」、「そういえばあれもできていなかったよね」と、あれもこれも色々と言ってしまうことはないでしょうか。
しかし、過去のことまで色々と言われると、お子さんは、今何について叱られているのかがわからなくなってしまいます。これでは、叱る意味がないですし、保護者の皆さんも色々思い出してしまって、最終的に「怒り」に変わってしまうことでしょう。
従って、叱る際には過去を頭の中から消してしまうように心がけましょう。
◎叱り方の注意点③否定や他の子との比較をせず、肯定的な言葉で具体的に改善策を伝える
「だからあなたはダメなの」といったような人格を否定するという言葉には愛情は存在しません。
自分を否定されたという意識で、子どもは傷つき、存在価値がわからなくなり、最悪の場合には心を壊してしまう恐れがあります。悪いことをした時であっても絶対に言ってはいけない言葉です。
同様に、「〇〇ちゃんはできるのになぜあなたはできないの」と、他の子どもと比べて叱ることも絶対にしてはいけません。
叱る際に必要なのは、子どもが親からの愛情を実感でき、安心できる心理状態にあることです。
そのためには、「自分=親」を主語にしたアイメッセージで「〇〇をしてくれたら嬉しいな」と肯定的にお願いをすると良いでしょう。むやみに否定的な注意をしても、子どもはどうしてそうしてはいけないのかが分からず、むしろ反対に注意した行動に興味を持ってしまうからです。
例えば以下のように言い換えるといいでしょう。
- 走らないで!→「ママ(パパ)と一緒にゆっくり歩いてくれたら嬉しいな」
- なんで挨拶ができないの!→「お客さんが来たら挨拶してくれたらママ(パパ)は嬉しいな」
- 早く片付けなさい!→「もうすぐ寝る時間だから〇〇ちゃんがお部屋を綺麗にしてくれたら嬉しいな」
子どもは、自分のすることが大好きなママ(パパ)を喜ばせていると思い、素直に行動を変えることができるようになります。
◎なるべく叱らないようにするための5つのStep
ここまでは叱る際の方法についてお伝えしましたが、できることなら叱らずにしたいものですよね。
ここからはなるべく叱らないようにするためにする5つのStepを紹介していきます。
◎Step①あらかじめ注意点を伝えたり、やってはだめなことを約束しておく
当然のことですが、子どもは圧倒的に経験が少なく注意すべきことや、やってはだめなことが判断できません。子どもの行為のほとんどが、無知から来ていることをまずは理解しましょう。
外に出かける際には「道路を渡るときは、左右をしっかり見て手を挙げてわたると、車からも〇〇ちゃんがよく見えて安全なんだよ。道路に飛び出すと車は急に止まれなくて轢かれちゃうことになるよ」と伝えることで、初めてのことでも子どもはどうしたらよいのかがわかります。
同様に、電車に乗る前に「電車の中では大声を出さないようにしようね」とお子さんと約束をしておきます。こうすることで、もし大声を出して叱られたとしても自分が悪かったとわかるので、子どもの中にも納得感が生まれます。
そして、教えたことができた時には全力で褒めてあげてください。万が一出来なかった場合には、理由をもう1度伝えて注意しましょう。
◎Step②(守れなかった時、怒らず)質問する、答えに共感する
約束を守れなかった子どもは、本当に悪い子なのでしょうか。
約束を守れない子どもの大半は、約束をうっかり忘れてしまっているのであり、悪いことをやろうと考えてやっているわけではありません。子どもの意識に定着していないから、うっかり忘れてしまうのです。
定着させるには、破ってしまったら即叱るのではなく、「こういう時はどうするんだっけ?」「守ろうとお話ししたルールはなんだっけ?」といったように質問して子どもに考えさせることが重要です。理解が深まり、意識は定着していきます。
小さな子どもには難しいので、そんな時は身近な人に例えてみると良いでしょう。
例えば「ママ(パパ)が誰かにぶたれたらどう思う?」というような質問をしてみるのです。
質問に対してかえってきた答えに対しては必ず共感してあげてください。
そこに信頼関係が生まれ、きっと次は守ろうと感じてくれる筈です。
◎Step③実現可能な約束をする
一方的に親が決めた約束をお子さんに押し付けがちですが、子どもと一緒に考えて話し合って約束を決めることが大切です。自分で決めた約束を守ることができた時、その成功体験から「自分はやればできる」という気持ちになり、自信がつきます。
約束を守る体験をさせるためには、必ず実行できる小さな約束をすることから始めてください。
「ここから、3問は終わらせよう」「後10分だけ頑張ってみよう」といったような、すぐに結果が出る約束をするわけですも効果的です。
これはスモールステップといって、目標とする事柄を段階ごとに細かくわけ、少しずつ、習得できるようにする考え方で、とても効果的な手法です。

スモールステップに適した教材としてRISU算数が挙げられます。1問ずつの問題は数分で解くことができます。
毎日の決まった時間に8分間だけRISU算数に取り組むのを約束して、1年半ほどで6年生のカリキュラムまで進んだ子もいます。
早川君 小3(当時)
四谷大塚 全国統一小学生テスト 全国No.1中学受験を考えており、2年生の春からRISUを始めて、1日8分、決まった朝の時間にコツコツと進めていました。
1年半ほどで6年生の内容まで進みました。3年生の2月より本格的に通塾が始まりますが、RISUのおかげで良いスタートラインに立つことが出来ました。ありがとうございました。
◎Step④(できたら)褒める
約束を守ることができたら、しっかりと褒めてあげてください。
もし出来なかったとしても、努力に対しては褒めてあげましょう。
子ども達が叱られるようなことをする一因として、気を引こうとしたり、自分が受け入れられているのかを探るためにわざと困らせるような行動を取るという「試し行動」があげられます。
この行為を防ぐには子ども達が「自分をしっかりと見てくれているんだ」「受け入れてくれているんだ」という気持ちを持てるようにしなければなりません。
例えばRISU算数では問題の解説とは別に「励まし動画」を配信しています。
子どもたちのやる気を上げることで、学習を継続できる構造になっているのです。

しっかりと褒めてあげることで、少なくとも気を引きたくて叱られるようなことはなくなるでしょう。
◎Step⑤(できなかったら)目標を下げてスモールステップを活用しよう
いつも上手くできなくて叱られていてばかりでは、子ども達は頑張ろうという気持ちになれる筈がありません。
約束通りにできなった時は、スモールステップを取り入れて目標を下げ、上手くできたという達成感を子ども達と共有しながら、次のステップへ向かうモチベーションを高めていくようにしましょう。
約束した10分間の勉強が出来なくて叱ってしまうよりは、「5分勉強できたんだ、えらいね。じゃあ、あと3分頑張ってみようか」、「今日は8分勉強できたね、明日は10分に挑戦してみようか」と出来たことを褒め、実現できそうな次の目標を提示しましょう。
RISU算数では、初回に実力テストを行ってから、スタートポイントを設定。年齢や学年にとらわれず、最適な目標からはじめる事で、成功体験を積み重ねることができます。
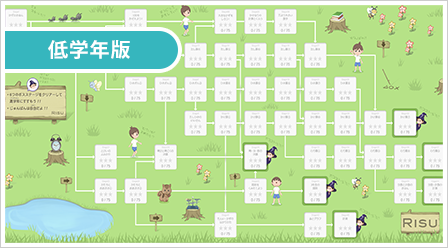
親御さんも子ども達も「どうしてできないの」を繰り返すより、「またできた」を繰り返す方が何事にも自信をもって取り組むことができるようになります。
目標は何度変更しても構いません。上手にスモールステップを活用してみてください。
◆それでも感情的に怒ってしまった時は
親も人間ですので感情的になり、怒ってしまうこともあります。
「あぁ、またやってしまった」と落ち込むよりもまず、子どもに謝りましょう。
抱きしめてあげて、目を見て謝り、どうして怒ってしまったのかを説明してあげれば、子どもには自分が愛されていること、信頼されていること、認められていることが伝わります。
ひとつひとつの行動についてではなく、しっかりと親子の関係が築けているかどうかを考えながら行動していけば、なるべく叱らないように過ごすことができる日々はきっと訪れるでしょう。