
小4の算数は急に難しくなり、つまずく子供が一気に増えます。
それが「小4の算数の壁」と呼ばれるものです。
新しい数字の概念も登場するため、ほとんどの子供は少なからず壁にあたると言われるほどです。
とはいえ、適切な対処法を知っていればそれほど恐れることはありません。
小4の壁攻略のポイントはズバリ「応用力」と「読解力」。
本記事では小4の算数の壁をテーマに、壁の理由と対処法を網羅的に紹介しています。
「小4の算数の壁」に不安をもつ親御さまは、ぜひ記事内容をご確認ください。
目次
なぜ小4に算数の壁があるのか

小4の「算数の壁」の主な原因は、低学年までの算数になかった「応用力」と「読解力」が求められるようになることです。
「算数の壁」となる2つの原因について詳しく解説していきます。
「【小学生】春休みはいつからいつまで?新学期から成績アップする過ごし方を紹介(学び相談室)」
「応用力」を必要とする問題が増える
低学年の間は、足し算や引き算、九九など、基本的な計算の要素が理解できれば簡単に解ける問題がほとんどでした。
しかし小4になると、面積の求め方や、分数の計算、小数やがい数の概念、複雑な計算方法など、今までならってきた基本的な算数の知識を応用しつつ、発展させなければ解けない問題が増えます。
特に分数や少数といった抽象概念の登場は、一気に算数を身近に感じにくくします。
そのため小4で算数につまづいてしまう子供が急激に増えるのです。
小4の壁は、応用力のベースとなる「基礎的な理解が本当にできているか」が試されるチェックポイントと言えます。
「読解力」を必要とする問題が増える
小4になると、算数の文章問題も低学年までの内容から一気に複雑になります。
低学年までの算数は、文章に出てくる数字を何となく使えば正しい答えが出せるものが大半。
「問題を論理的に正しく理解する」ということを、あまり意識する必要がなかったかもしれません。
しかし小4では分数や少数といった抽象的な概念、面積を求める公式などが登場します。
算数独特の用語や複雑な公式が増える中で、「文章中の何が何を指すのか」を正しく理解しなければ、式を立てることができず、正解できなくなってしまうのです。
こうした読解力の不足も、小4で算数の壁にぶつか原因になります。
小4「算数の壁」から劣等感へ 悪循環を招くケースもある
小4の頃(9~10歳)は、自我の目覚めが現れ始める時期です。
集団の決まりを意識しつつ、その中で自分の立場や役割を考えるようになります。
自分を客観視できるようになるため、算数への苦手意識が高まることで「自分はできない人間だ」と思い込み、自己肯定感を下げてしまう可能性もあります。
参考サイト:文部科学省 「子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課題」
学習のつまづきによって、学校生活のストレスが大きくなり、家庭でのコミュニケーションがうまくとりにくくなるのもこの時期です。
「小4の算数」の壁をうまく乗り越えることは、子供の心を安定させ、学校生活や家庭生活を穏やかに過ごすために重要なポイントになるのです。
小4で「算数の壁」を実感したら迷わずつまづきポイントに戻る

算数は国語や社会などの科目と違い「積み上げ」の教科です。
小学3年生までにならった基礎を元に、小学4年生で初めて大きなステップアップに直面します。
したがって、小学4年生の算数でつまづき始めた場合、すみやかに小学3年生(もしくはそれ以前)の単元に戻って学び直しをしなければいけません。
そのままにしておくと、すぐに算数の授業についていけなくなってしまいます。
しかし、つまづきポイントに戻るのは子どもにとって少し勇気が必要です。
まず、自分が理解できていないことを認めなければいけません。
授業は小学4年生の内容を次々に進めていきますし、周りの子たちが理解しているようだと、なおさら自分ができないことを認めたくない気持ちが働きます。
後戻りして学習し直すのは子どもの心にとってハードルが高いため、上手く家庭でのサポートをしてあげる必要があります。
小4でつまづきやすい算数の単元
「応用力」が特に必要とされ、算数の壁となりうる単元が以下の5つです。
・角度の計算
・割り算のひっ算
・分数の足し算と引き算
・小数の計算
・がい数計算
角度の計算
角度の計算は図形の「理解力」と「計算力」の両方を必要とする単元です。
角度計算の難しさは与えられている角度と図形をよく見て、すでに角度がわかっている箇所を自分で発見しなければいけない点にあります。問題を解くためのカギを自力で探し出すイメージです。
計算ドリル問題は最初から計算式が与えられているため、あとは解くだけでよいのですが、角度の計算は自分で計算式そのものを導き出さなければいけません。
問題を解く手がかりを探し出すために、数字を書いたり補助線を引いたりする手作業も必要です。
頭の中で計算を進める方法に慣れている子供は、角度問題を頭の中で解こうとするため、つまづく可能性が高くなります。
割り算のひっ算
「割り算のひっ算」は、小4の算数の壁の代表ともいわれる単元です。
小4の算数では、1桁から3桁までの数で割り算をするようになるため、割り算のひっ算を学習します。
割り算のひっ算は、計算に慣れてケアレスミスにさえ気をつければ、スムーズに解ける構造になっていますが、慣れるまでにどこに数字をおけば良いのか、足すのか引くのか、注意すべきポイントはたくさんです。
小3までに学習したさまざまな算数の要素を使って問題を解くため、割り算のひっ算でつまづいてしまう子供が多く存在します。
分数の足し算と引き算
単純な分数の計算問題はできても、文章題で出題される分数計算でつまづいてしまう子供はとても多いです。
分数の基本的な概念を理解せずに小学4年生まで来た子供は、分数の文章題でことごとくつまづいてしまいます。
小4時点で分数の概念や比較的簡単な文章問題でつまづいてしまうと、後々さらに難しい問題に直面したときに完全にお手上げになってしまいます。
子供が分数計算でつまづいていないか、家庭でもよくチェックしておきましょう。
もしつまづいているようであれば、必要に応じてサポートが必要です。
小3のお子さんへの分数の教え方についてはこちらの記事をお読みください。
小数の計算
小数の計算は分数の計算と同様に苦手意識をもつ子供が多いです。
主な理由は、イメージしやすい1や2などの整数と違い、分数や小数は日常生活の中でイメージしにくいこと(=抽象概念)が挙げられます。
小数の学習は、整数以外で表現される新しい世界へ進む感覚です。
戸惑いとつまづきがあるのも致し方ありません。
例えば小数の掛け算をすると、もとの数よりも答えが小さくなることがあります。
整数の掛け算ではあり得ないことです。
1以下の小数の掛け算や割り算は異次元の世界で、正しく理屈を理解しなければつまづく可能性が高まります。
小数のかけ算・わり算の教え方についてはこちらの記事をお読みください。
がい数計算
がい数計算は、大きな桁の数字が並ぶため、それだけでとっつきにくさを感じてしまいます。
苦手意識をもつ子供が多いのも無理もありません。大きな数字に面食らってしまい、心が折れるイメージです。
桁の大きな数をがい数で考える作業は、日常生活とかけ離れていることもイメージしにくくとっつきにくい原因の一つです。
がい数は、およその数・四捨五入の単元で学びます。
まず億や兆の数の概念を学んだ後にがい数で数える方法を学んでいきます。
およその数・四捨五入はこの後中学生にかけて学ぶ平均や数列・べき乗など数の概念を考えるための入口となる大事な単元です。
小4の時点でつまづくと、今後学ぶ「平均」「数列」などの単元が理解できず、お手上げ状態になってしまいます。
重要度の高い単元と認識しておきましょう。
小4で算数の壁の原因になる小3の算数
小4の算数の壁とはいうものの、実際には小3の算数こそが小4算数のベースになっています。
算数は積み上げ式の教科。
小3の大事な単元が理解できないままにしておくと、確実に小4の算数の壁にあたることを認識しておきましょう。
抑えておきたい大事な単元を3つピックアップしました。
・時間と時刻
・余りのある割り算
・◯(マル)を使った計算
時間と時刻
時間と時刻の問題では、以下のような形式で出題されます。
「午前11時15分から午後1時30分までは何時間何分でしょうか」
「午後3時は24時間表記では何時でしょうか」
3年生で習う時計の問題が理解できないと高学年で習う速さの問題が解けなくなります。
時間や時刻の概念は生活の中で、誰でもいつかは理解できるようになるため、喫緊の問題ではありませんが、中学受験を考えている場合は早めに対処しておいたほうが良いでしょう。
もし子どもが時間と時刻でつまずいているようであれば、以下3つのポイントを理解できているか、確認してみましょう。
・12時間と24時間の表記を変換できるか
・時間の経過は引き算で導き出せることを理解しているか
・時間計算では1時間60分に換算することを理解しているか
時間と時刻は日常生活の中でイメージしやすいため、家庭でのサポートもしやすいです。
余りのある割り算
小3になると割り算が登場します。特に「余りのある割り算」でつまづく子どもが多いです。
余りのある割り算は主に、以下のような形式で出題されます。
「みかんが30個あります。4つの箱に分けるとすると1つの箱にみかんは何個入りますか?
そして余りはいくつでしょう?」
子供が余りのある割り算でつまづいた時のチェックポイントは以下の2つです。
・割り算に必要な九九を正しく理解しているか
・余りのある割り算に必要な足し算と引き算を正しく理解しているか
もし掛け算が危ういようであれば、小2の単元に戻って学習しましょう。
小3で割り算を習得しておかないと、小4ではさらにわからなくなります。
◯(マル)を使った計算
◯を使った計算は、問題文の隠された数量を◯で表して足し算や引き算を使い、答えを求める問題です。
以下のような形式で出題されます。
「箱の中にみかんとりんごが50個入っています。りんごは32個でした。みかんは何個でしょうか?」
「せんべいが◯枚入っている缶が8つあります。せんべいの数は全部で40枚です。一つの缶にせんべいは何枚入っていますか?」
もし、子供がこの単元を苦手にしているようであれば以下2つのポイントを確認してみましょう。
・何を◯として考えればよいのか理解しているか
・文章を数式であらわすことができるか
わからない場合は「何を聞かれているのか」「分からない数字はどれか?」など、出題された文章をゆっくり整理してみましょう。
文章問題の「読解力」を身につける方法
文章問題を正しく理解し、解けるようになるにはどうしたら良いのでしょうか。
具体的な対処方法を3つ紹介します。
文章問題の理解には音読が効果的
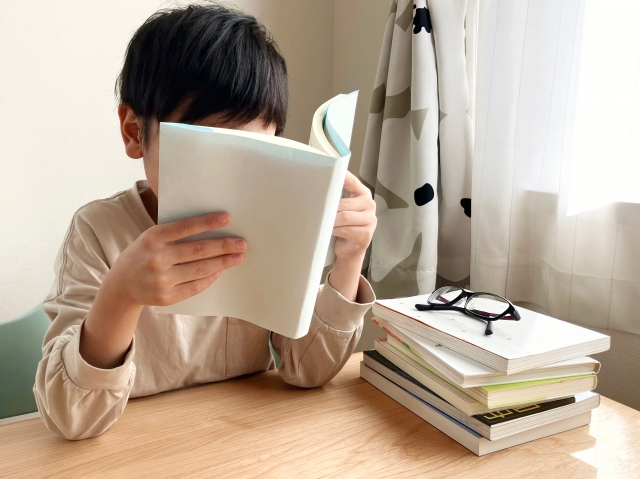
問題文が理解できない子供でも、声に出して問題文を読み上げてみるとあっさり理解できることがあります。
実は黙読の場合、問題文を目でなぞっているだけになっている子供が多いのです。
問題文が苦手な子供は文章が長くなればなるほど苦手意識が高まっていき、おおよそ3行を超えると長いと感じてお手上げ状態になると言われます。
問題文が苦手な子供には、まず音読してみることをおすすめします。
文章問題の復習を習慣化する
小3までの文章問題自体は単純なものが多いですが、概念をしっかりと理解しているかは文章問題を解けるかで分かります。
単元を混ぜて文章問題を解かせてみると、範囲の無いテストになるので、子供の本当の理解度を確認することができます。
そして復習のサイクルを普段の勉強にうまく取り入れると、知識が定着し、自在に知識を使いこなせるようになります。
今日習ったことの復習とは別に、ずいぶん前にならったことの復習も取り入れるようにしましょう。
ポイントは決まった時間に継続して復習をすることです。
生活の中でできる小4「算数の壁」対策

家庭生活の中でもできる算数の壁対策を3つ紹介します。
・お買い物の中で学習する
・親が自分のために本を買う
・知育に役立つ学習アプリをつかう
お買い物の中で学習する
スーパーやその他小売店などには、算数に関する多くの学びがあります。
例えば、「がい数・およその数」に関する内容では、よくある2,980円などの商品が活用できます。
子供に2,980円の商品を3個かうためにはいくら必要か、聞いてみましょう。
子供は2,980円の計算を暗算で試みようとするかもしれません。
そこで、がい数の概念の登場です。2,980円を3,000円に設定して、必要となるお金は9,000円、この考え方ががい数・およその数、と説明します。
がい数の他には、分数、割合、単位などもスーパーなどの小売店を学びの場にできます。
身近な具体例を使って学習を先取りしておくと、子供の学校での学びを質の良いものにしてくれます。
「小学生のお小遣いはいくらがふつう?お金の勉強になるのはどんな渡し方ですか?(学び相談室)」
親が自分のために本を読む
子供が本を読み、言語に触れる機会を増やすことは思考能力の育成にとても効果的です。
とはいえ、言語能力の不十分さは、算数の学びに不都合が生じるものですが、言語能力は一朝一夕に身につくものではありません。
日々の過ごし方や言語とのふれあいがとても大切です。
本好きな子供に育てるための方法はいくつも紹介されていますが、「親が自分のために本屋で本を買う」という方法は効果があります。
ネットで本を買う機会が増えつつある昨今ですが、ポイントはリアルな本屋で選んで買うことです。
親が本を選んでいる間、子供は子供向けの本のコーナーで待ってもらうのも良いですし、親と一緒に本選びに付き合ってもらうのも良いです。
子供が自分で興味ある本を見つけてきたらぜひ買ってあげましょう。
もし、子供が本に興味を示さなかった場合でも、幼少期に本に接する機会が多ければ先々何かのきっかけで本に興味を持つようになるかもしれません。
学習アプリやタブレット教材をつかう
学習アプリやタブレット教材は、家庭教育で効果を発揮します。
教師がいなくとも正解と間違いの判定ができ、それぞれの子供のレベルにあわせた問題に取り組める点はアプリならではのメリットです。
紙の教材と違い、間違えた問題に繰り返し取り組むのも簡単にできます。
小4の算数につまづいたら小3や小2の単元にもどってやり直ししなければいけません。
しかし、実際には子供のプライドが邪魔をして、すんなりやりなおしとはいかない現実があります。
無学年制カリキュラムやゲームのような世界観など、子供のプライド問題をうまく考慮して作られているものも多く、意識せずに過去の復習ができます。
生活に身近になったスマートフォンや携帯ゲーム機などとの付き合い方はとても難しいです。
とはいえ、今の子供たちが生きていく社会ではスマホなどの情報機器との関わりは、避けて通れる道ではありません。
良いところは積極的に学習へ取り入れていきましょう。
「RISU算数」なら自立的な学習習慣が身につく!
算数専用タブレット教材の「RISU算数(幼児向けサービスは「RISUきっず」)」には、
4歳から小中学受験基礎に加え中学数学基礎までの約10000問を収録。
計算問題だけではない、算数の学力全体を伸ばすことができます。
お子さんの算数の学力を効率よく伸ばせる「RISU算数」の特長を3つご説明します。
特長1:図形問題や文章問題が豊富
RISU算数には、図形問題や文章問題など幅広い算数の問題が収録されており、
中学入試や算数オリンピック問題など、思考力を試す問題も多く含まれています。
進学塾に通っているお子さんであっても、
計算力は高いのに文章を読み取るのが苦手で問われていることを正確に理解できないお子さんや、
論理的に考えるのを苦手としているお子さんは多くいます。
RISU算数では、基礎的な計算問題からハイレベルな文章問題まで、
算数の学力をバランスよく伸ばすことができます。
特長2:無学年制カリキュラム
RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。
学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、
つまずいた分野では学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。
紙のテキストのように何学年分も用意する必要はありません。
またRISU算数ではデータに基づき、お子様の学力に合わせた出題がなされるため、
難しすぎて勉強が嫌いになってしまうということや、簡単すぎて退屈するということもありません。
つまり、解き甲斐があり楽しい問題がつづくため、
自然にどんどんと先へ進めることができてしまうのです。
特長3:豊富な解説動画
RISU算数では、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が大人気。
分からない問題も、解説動画を見てお子さん一人で解決することができます。
また定期的にチューターからの応援メッセージ動画を楽しみにされているお子さんもたくさんいらっしゃいます。
憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適です。
他にも、自動採点機能やメールで学習進捗をお知らせする機能など、保護者の方にも嬉しい機能が満載。
共働きや小さいお子さんがいるなど、毎日忙しい親御さんも安心してお子さんの学習を見守ることができます。
まとめ
小学4年生になると、それまでに習った算数の知識を前提とした「応用力」が必要となる単元が次々に登場します。
すでに理解している前提で授業は進むため、理解が不十分な子どもは算数の授業についていけなくなります。
特に文章問題を苦手とする子どもも増えるので、「読解力」は小さなころから意識してつけておいたほうが良いでしょう。
つまづきを感じたら、前の単元にもどって再度理解できるまで学習すると解決できるのですが、実際には簡単にいきません。
そんな時は、学習アプリやタブレット教材を試してみてください。子供の「わからない気持ち」に配慮した作りになっているので、紙での学習が合わなかったお子さんにこそおすすめできる勉強方法です。
RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。
中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。
RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。
ぜひ一度お読みください!
RISU算数の効果や料金を紹介┃利用者の評判はどう?(おもすく)


























