
「どうしたらひらがなが読めるようになる?」
「ひらがなが読めないのは発達障害?」
と、気になる方に向けて、5〜7歳でひらがなが読めない場合に考えられる原因や、発達障害との関連、ひらがなが読めるようになる方法を解説します。
子どもがひらがなを読めなくて不安な方は、ぜひ参考にしてください。
目次
ひらがなが読める年齢とプロセス

まず、ひらがなが読めるようになる年齢や、ひらがなを読むためにどのような能力が必要なのか確認していきましょう。
年長児の7割がひらがなをほとんど読める
年長の冬から小学校1年生の夏までに、ひらがなを読めるようになっているのが目安です。
年長児(5・6歳)では、7割の子どもが、濁音などを含むひらがな71音をすべて読めるか1音間違えるといった調査結果があります。
また、年長でひらがなを読めない子どもの9割は、小学校1年生の2学期には追いつくという結果もあるため、就学前にひらがなを読めない子が、その後ずっと読めないままというケースはほとんどありません。
しかし、小学校1年生の4月にはひらがなの書き方を習うことを考えると、年長から少しずつ読めるようにサポートしていくと良いでしょう。
(参考:宇野 彰ら、「ひらがなはいつまでにどれだけ習得されるのか ? ─ひらがな習得に関するレディネス─」/高次脳機能研究 2021年 41巻 3 号 p. 260-264)
ひらがなを読めるようになるプロセス
ひらがなを読むのは、子どもにとって複雑なプロセスがあります。
- 眼球を動かし、焦点を合わせる
- ひらがなの形を識別する
- ひらがなに合う音を頭の中で検索する
- 単語や文節のまとまりを認識する
- 発声する
ひらがなが読めない、またはたどたどしい場合、このどこかのプロセスでつまづいている可能性があるでしょう。
眼球の運動・ピント調節がうまくいかない目の機能の問題や、形の識別が困難である視覚認知の問題、音への変換がうまくいかないといった問題が考えられます。
また、文字を読む初期段階では、語句や文節を1つのまとまりで認識できず、「り・ん・ご」といったようにたどたどしく読みます。
ひらがなを、単語や文節のまとまりで捉えることも、ひらがな習得には重要です。
幼児でひらがなを読めないとその後どうなる?
年中(4・5歳)でひらがなを読めなくても、興味が出ると数か月で一気に読めるようになる子は多いため、過度な心配はいりません。
また、年長(5・6歳)でひらがなを読めなくても、ほとんどの子どもが小学校1年生の夏までに読めるようになります。
ひらがなの習得に苦労する原因によっては、漢字の読み書きや英語の学習で苦労する可能性がありますが、早期のトレーニングで改善が期待できます。
海外の研究で、読む能力に問題がある子ども6歳〜9歳に、適切な音韻指導をおこなった結果、言語発達に問題のない子ども達と同じ脳の使い方ができるようになることが判明しているためです。
焦らず、ひらがなの読み方を根気よく練習していきましょう。
(参考:Shaywitz, Bennett A et al. “Development of left occipitotemporal systems for skilled reading in children after a phonologically- based intervention.” Biological psychiatry vol. 55,9 (2004): 926-33. doi:10.1016/j.biopsych.2003.12.019)
ひらがなが読めない・覚えられない4つの原因

ひらがなの読みを覚えられない原因には4つの理由が考えられます。
- ひらがなに興味がない
- 聴覚性短期記憶が苦手
- 音韻の処理がうまくいかない
- 視覚情報の処理がうまくいかない
それぞれの原因について詳しく確認していきましょう。
理由①ひらがなに興味を持てない
とくに4・5歳でひらがなが読めない場合、そもそもひらがなに興味がないという理由が多いです。
- 文字に触れる機会が少ない
- 身近な大人があまり文字を読まない
- 他の好きなことに夢中
絵本をあまり見ない・外遊びが大好きで一日中公園にいるなどで、文字に触れる機会が少ない子は、なかなかひらがなに興味を持てません。
文字という抽象的な記号を覚え、理解するのは幼児には難しいものです。
ひらがなを読めるようにするには、ひらがなへ興味を持たせることが必須です。
理由②聴覚性の短期記憶が苦手なため覚えられない
ひらがなを覚えるには、読み方を耳で聞き、音を一時的に記憶し、ひらがなと結びつけて処理する必要があります。
聞いたことばを頭の中にとどめておく聴覚性の短期記憶が苦手な子は、ひらがなの読み方を教わってもなかなか覚えられません。
理由③音韻を意識できない
ひらがなの読み方を覚えられない代表的な原因の1つが、音韻意識の不足です。
音韻とは、言語の最小単位のことです。
日本語の音韻では5個の母音(あいうえお)と14個の子音(k、s、tなど)を組み合わせますが、この音韻を意識できないと、ひらがなの読みを習得できません。
たとえば、「お」が、「おう」「ぅお」「おお」など曖昧になってしまうため、覚えるのに時間がかかってしまうのです。
ひらがなの読み方を覚えるのに、音韻意識は重要です。
理由④形の認識が難しい
ひらがなを覚えるには、まずひらがなの形の違いを認識しなければいけません。
線と線の間隔や交点、曲線、ハネを視覚的に捉えることが、ひらがな習得には重要です。
大人でも、アラビア語などあまり見慣れない言語の文字を見ると、文字の違いが分かりにくいのではないでしょうか。
子どもも同じで、ひらがなに慣れないと形の違いを認識できません。
また、空間認知機能が未熟であったり、文字を読むときに視線がずれてしまう場合も、ひらがなの形を正しく認識できず、ひらがなを読めない原因となります。
小1でひらがなが読めない場合に考えられる学習障害(発達障害)
小学校1年生で、ひらがなの読み方が分からない場合は、文字の習得に何かしらの困難を抱えているかもしれません。
ここでは、文字の読み書きに関する学習障害や発達障害について解説します。
ひらがなが読めないと学習障害・発達障害の可能性がある?
小学校1年生で、ひらがなの読みを覚えられない場合に考えられる発達障害の代表的なものが、ディスレクシア(読字障害・書字障害)です。
ディスレクシアの子どもは、読むのに時間がかかって間違えやすい特徴がありますが、まったく読み書きができないわけではありません。
とくに6〜9歳のあいだに適切なサポートや指導をおこなうことで症状が大幅に緩和されることが分かっています。
そのほか、考えられる発達障害は注意欠陥・多動性障害(ADHD)です。
ADHDの子どもは、注意力が散漫になったり、気が散ってしまうなどで、文字をじっくり読めず、文字や文章が読めないという症状が出ることがあります。
ディスレクシアの特徴とチェックリスト
ディスレクシアの特徴はこちらです。
- ひらがなに苦手意識がある
- 覚えたと思ったらすぐ忘れる
- 読もうとするとすぐに疲れる
- 1文字ずつ指追いしながら読む
- 黙読が難しい
- 文字が歪んで見える(白黒が反転して見える・滲む・鏡文字に見えるなども)
- 知的な遅れはない
これらの症状に当てはまるからといって、かならずディスレクシアとはかぎりません。
とくに、ひらがなの覚えはじめでは、すぐ忘れたり疲れるものなので、あくまで参考としてください。
ディスレクシア疑いの子どもへの公的支援
ディスレクシアは、さほど珍しい疾患ではありません。
通常学級に在籍する子どものうち、3.5%が読み書きに著しい困難をきたしているという調査結果があります。
(文科省「令和4年 通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する 調査結果」p26)
1クラスに1名前後はディスレクシア疑いの子がおり、小学校も読み書きが難しい子どもの存在を理解しているため、まずは学校の先生に相談しましょう。
子どもの特性を踏まえて、プリントや宿題などを工夫をしてくれることがあります。
また、自治体の発達支援センターや発達相談窓口へ相談すると、医師・心理士との面談や言語聴覚士のサポートを受けられます。
児童精神科や発達外来を直接受診して相談・診断してもらうことも可能です。
「子どもが「人の話を聞けない」原因は?子どもの「話を聞く力」を高める方法を知りたい(学び相談室」
家庭でできる!ひらがなの学習方法とおすすめ教材
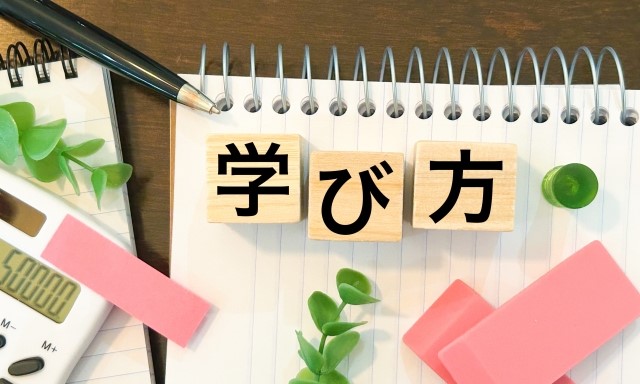
ひらがなが苦手な子どもに効果的な学習方法をまとめました。
- ひらがなに興味を持たせる
- 文字を大きくする
- 音韻を意識する
- 自動化する
- 目の運動をする
- 語彙を増やす
具体的に解説するので、ぜひ取り組んでみてください。
ひらがなに興味を持たせる
5歳前後でひらがなに興味がない場合は、子どもが主体的にひらがなの学習ができるように、遊びやゲームを通して興味を持たせましょう。
幼児向けのカルタは、ひらがなが読めなくても絵柄で札を取れるのでおすすめです。
また、好きなキャラクターの名前やお店の名前、自分の名前を紙に大きく書いて、一緒に読んでみましょう。
ひらがなが書かれた積み木や、ひらがなを押すと音声で教えてくれるタブレットは、ひらがなに興味を持たせるのにおすすめのおもちゃです。
「ええ!これが読めたの?いつの間に?びっくりしちゃった!」
「おしい!これはこう読むんだけど、読もうとするなんてすごい!」
と間違ってしまっても大げさに褒めると、ひらがなに興味を持てるようになります。
視覚認知を助ける(文字を大きくする・点つなぎをする)
小さい文字は、ひらがなの形を視覚的にとらえにくいため、文字を大きくしましょう。
お煎餅ほどの大きさのひらがなをマジックで紙に書き、ひらがなカードやひらがなノートをつくって読む練習に使用してください。
ひらがな表を拡大プリントするのもおすすめです。
また、点つなぎや間違い探しで遊んでみましょう。
点つなぎや間違い探しなどの空間認識力を高める遊びは、ひらがなの線や交点の位置関係を認識しやすくなり、ひらがなの形の違いを意識できるようになります。
1つのひらがなに1つの音!音韻を意識する
日本語の母音・子音を意識して発音できるように練習しましょう。
音韻を意識できていないと、例えば「お」が「おぅ」「おぉ」「ぅお」等あやふやになってしまい、ひらがなを覚えられない原因となります。
- 手を叩きながら発音する
- 階段を1段ずつ上りながら発音する
これらの方法で、1つのひらがなに1つの音が当てはまることを意識できるようにします。
たとえば、「きりん」であれば、「き」手を叩く(1段上がる)、「り」手を叩く(1段上がる)、「ん」手を叩く(1段上がる)といったようにおこないましょう。
自動化して瞬時に分かるようにする
保護者の方がひらがなカードを見せ発音したら、子どもにすぐ発音を繰り返してもらう練習を繰り返して、ひらがなの読みを自動化させましょう。
保護者が「あ」のカードを見せながら「あ」と言い、子どもにすぐ「あ」と言ってもらいます。
反射的に発音させることで、頭の中で文字に対応する音を探す作業を省き、無意識に読めるようにします。
聴覚的な短期記憶が苦手な子のひらがな学習や、英語学習にも有効ですので、ぜひ試してみてください。
目の運動をして眼球がスムーズに動くようにする
目の動きがぎこちないと、次にどの文字を読むべきか分からなくなるため、目の運動も取り入れましょう。
ひらがなを読むには、視線を数ミリから数センチ単位で微調整する必要があるため、眼球の運動をスムーズにする必要があります。
- 視線を左右にゆっくり動かす
- 視線を上から下にゆっくり動かす
- 視線を時計まわり・反対まわりに動かす
眼球の周りについている筋肉をほぐすように、ゆっくり動かしましょう。
保護者の指や、小さなマスコットをなどの小物を用いて視線を誘導してあげるとうまくいきます。
語彙を高めて語句・文節のまとまりを認識できるようにする
ひらがなを、語句や文節のまとまりで読めない場合は、語彙力を高める学習をおこないます。
- 絵本などから語句を選ぶ
- 意味を教える
- 例文を一緒につくる
- 語句や例文を音読する
たとえば「いなびかり」であれば、雷の光のことで音は含まないのだと教えます。
「遠くにいなびかりが見えた」などの例文を一緒につくって音読し、語句の読みと意味を定着させましょう。
ひらがなが読めない子どもとの関わり方

ひらがなが読めない子どもは、文字に対して苦手意識を持ちやすく、自信を失いやすい傾向があります。
ひらがなの習得に向け、子どもとの関わり方のポイントも押さえておきましょう。
読めるようになっても毎日5分練習する
子どもは、ひらがなが読めるようになったと思っても、数日経つと忘れてしまうケースが多いです。
とくに、ひらがなの読みを自動化する練習(保護者がひらがなカードを見せ発音したら、子どもに発音してもらう方法)は毎日コツコツおこないましょう。
誰かのせいではないので責めない
子どもにひらがなを教える際の大きなポイントは、責めずに褒めることです。
保護者の方は、なかなか文字を読もうとしない子どもを見ると、やる気がなく見えたり怠けているように感じるのではないでしょうか。
焦りや不安が大きく、つい子どもを責めてしまったという経験のある保護者の方も少なくありません。
しかし、ひらがなを読まないことを責めると、文字が苦手になったり自信がなくなったりと逆効果です。
算数など他の得意を伸ばす
ひらがながなかなか覚えられないと自信を失いやすいため、他の得意を伸ばして自己肯定感を育てましょう。
スポーツやピアノといった達成感のある習い事や、子どもの好きな分野で、自信をつけさせます。
また、数字に抵抗がなければ、算数の力を伸ばすのもおすすめです。
ひらがながあまり読めない状態で小学校に入学した場合、国語の学習に時間がかかってしまうため、少しでも算数を進めておくと子どもの負担を減らせます。
「【必修化】小学校のプログラミング教育はいつから?どのような授業内容なのか教えてください(学び相談室)」
ひらがなが読めない場合によくある質問

Q.ひらがなが読めない病気は?
発達障害の1つである識字障害(ディスレクシア)が考えられます。
しかし、ディスレクシアでは全く読めないわけではありません。
正しくは、読めるけれど間違えやすく、読むのに苦労する疾患です。
Q.ひらがなが読めるようになるのは何歳頃ですか?
早いと3歳ごろから読みはじめ、
年長時点でひらがなが読めなくても、小学校1年生の夏休み明けには他の子どもに追いついているという調査結果があります。
Q.5歳でひらがなを読める割合は?
5~6歳(年長)では7割の子どもが、濁音等を含むひらがな71音のほとんどを読めるようになっています。
5歳7か月~9か月の子どもの識字数調査では、71音中平均で61.5文字のひらがなを読めるという結果です。
Q.文章が読めないのは発達障害ですか?
注意欠陥多動症(ADHD)の方は、文章を読む際に気が散ってしまったり読み飛ばしてしまい、文章が読めないことがあります。
ただし、ひらがなを習得中の子どもは、語句や文節のまとまりが分からず、長い文章が読めないこともあるため必ずしも発達障害とはいえません。
算数を得意にするなら「RISU算数」
算数専用タブレット教材のRISU算数は一人ひとりでにピッタリとペースで無駄なく学習可能。
未就学児向けサービスの「RISUきっず」には問題の読み上げサービスがありますので、まだひらがなが読めないお子さんでも安心して算数学習に取り組めます。
RISU算数の算数が得意になる特長3つをご紹介します。
特長1 :無学年制カリキュラム
RISU算数では無学年制カリキュラムを採用。
学年を超えてどんどん先取り学習を進めることも、つまずき対策に学年を遡って復習することもタブレット一台で完結します。
またRISU算数では一人ひとりの学習データに基づき問題を出題。
難しすぎたり簡単すぎたりしないので、楽しく達成感のある問題が続きます。
そのため無理なく基礎を固めつつ、自然に先取り学習ができてしまうのです。
特長2:分かりやすい解説動画

RISU算数では解説動画が分かりやすい、と大人気。
分からない問題も、東京大学をはじめとするトップ大学生チューターによる解説動画が豊富なので、お子さん一人で解決することができます。
また定期的に届くチューターからの応援メッセージも好評。
憧れの大学に通うお兄さんお姉さんからのメッセージは、学習へのモチベーションアップに最適です。
特長3:ゲーム感覚でどんどん進む

タブレット教材のRISU算数なら問題を解いたら自動採点機能でその場ですぐに採点。
おうちの方が丸つけする必要がないので、お子さんだけでどんどん学習をすすめることができます。
テンポよくステージをクリアしていくことで、まるでゲームを攻略するように楽しんで進めることができつので、自然にお子さんの集中力を高めることができます。
また他にもメールで学習進捗をお知らせする機能や、RISUきっずでは問題の読み上げ機能など、保護者の方が安心して学習を見守れる機能が満載です。
ひらがなが読めない子どもへの対応まとめ
ここまで、ひらがなが読める年齢の目安や、原因・対応策を解説しました。
7割の子が就学前にひらがなを読めますが、読めない場合でも小学校入学後の数か月で身につくことが多いです。
ひらがなを読むには、小さな子どもにとって複雑なプロセスを必要とします。
今回ご紹介した、音韻の意識や空間認知能力を高める遊び、自動化するトレーニングをおこない、ひらがなを習得しましょう!
RISU利用者レビューでは、RISU算数をご利用いただいている保護者様の声をご紹介しています。
中学受験で志望校合格、大手塾模試で成績が大幅アップ、家庭学習の質が上がった、など皆様の参考になるリアルな体験談が多数。
RISU公式ブログでは、算数オリンピックメダリストや先取り学習での算数検定合格者、大手塾主催模試での成績優秀者など、お子様の声を中心にご紹介しています。
ぜひ一度お読みください!


























